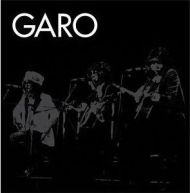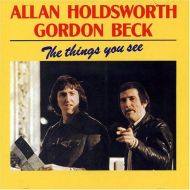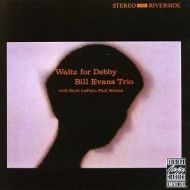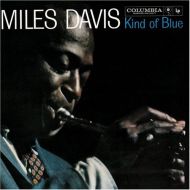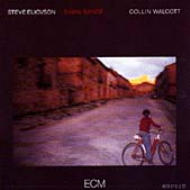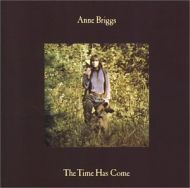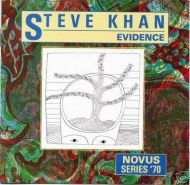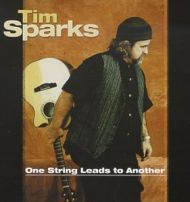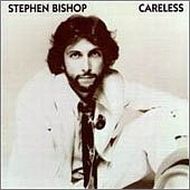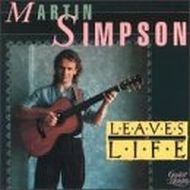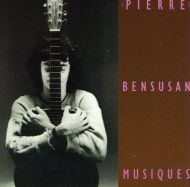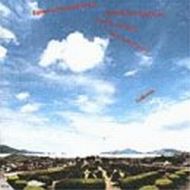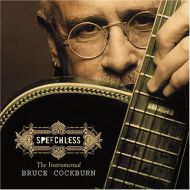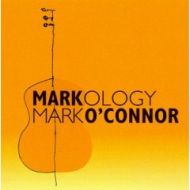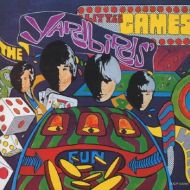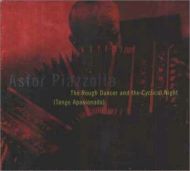2007年8月20日。東京勝どきの第一生命ホールでエグベルト・ジスモンチ(tiはポルトガルでは「ティ」と発音するが、ブラジルでは「チ」となるという話を聞いたので、今回からジスモンティではなくジスモンチと表記することにした)が16年ぶりに来日公演をおこなった。
ずいぶんと時間がたってしまったが、今回は特にCDを紹介するのではなく、このコンサートで感じたことを記してみたい。
前回の来日は1992年。関東ではBlue Note東京での公演だった。『Infancia』をリリースした直後ということもあり、ギター兼キーボード、ベース、チェロを加えたクァルテット編成で、とても完成度の高い素晴らしい演奏をおこなってくれた。
その後、大病を患ったこともあり、特に海外公演は滅多に行わなくなったので、生の演奏を見るにはブラジルに行くしかないのかもと思っていた矢先、突然の来日情報、それもソロコンサートだという。「このチャンスを逃すと二度と見ることができないかもしれない」という切羽詰った思いで、チケットを手配確保した。
会場の第一生命ホールは1,2階をあわせても800席弱のこじんまりとした楕円型のホール。
舞台のやや下手よりにはSteinway&SonsのフルコンサートピアノD-274(だと思う)。AKG C-414を2本,ややオンマイク気味に立てている。ほぼ中央には、ギター演奏に使う椅子と足台。こちらにはAKG C-491が一本。マイクはいずれもショックマウントを使用していた。
会場の規模からいって、ギターは生音なのかPAを使うのかは興味のあるところだったが、マイク録りでPAというスタイルだったわけだ。ただ、客席の両脇と、舞台上手のスピーカーの後ろにビデオカメラがセットされていたので、収録用としても音をきちんと拾う必要があったに違いない。
定刻からわずかに遅れて、会場の照明がおちる。舞台の袖からジスモンチが2本のギターを持って登場すると、会場から割れんばかりの拍手。彼の来日を心待ちしていた観客の気持ちがひしひしと伝わる。もちろん、私もその中の一人だ。
まず手にしたのは10弦のナイロン弦ギター。マイクの位置をちょっと直したかと思うと、いきなり演奏に入る。冒頭からものすごい疾走感。ピアノのポリフォニック的要素をギターで実現するために多弦ギターを使うといっていたが、確かに、左手のタッピング、右手の早いアルペジオやラスゲアードに近い奏法、また、ピッキングハーモニックスも多用していて、その音はまさしく変幻自在で、一本のギターから発せられているとはにわかには信じがたいほどだ。
よく、「ギターは小さなオーケストラ」とたとえられることがある。伴奏もメロディーも一台の楽器でこなし、音域も広いからだと思っていたが、ジスモンチの演奏を聴いていると、まったく違う次元で「ギター=オーケストラ」ということが理解できる。
時折12弦仕様のスティール弦(通常の12弦とは違い8弦ギターを部分的に複弦にしているように見える)に持ち替えながら6曲を演奏。どの曲もファンにはおなじみのメロディながら、アレンジが異なるせいか楽曲の色彩がいつもと違っているように感じる。それが、「現在のジスモンチ」の演奏という感をいっそう強くする。
息をつく間もなく前半が終わり、しばしの休憩。
ロビーに出ると、皆が興奮の色を隠せず、そこかしこで今日の演奏について言葉を交わしている。
そうこうしているうちに後半の始まりを告げる合図があり、あわてて席に戻る。
後半はピアノのセット。ピアノの前に座ったジスモンチは、まったくもったいぶることなくいきなりトップギアに入れての演奏が始まる。ただし、コンテンポラリー色の強いギターと比較すると、ピアノの演奏スタイルはいたって正攻法。クラシックのピアノになじんでいる人にとっては違和感があるのかもしれないが、とてもよく歌うフレーズはきわめて心地のよいもの。
ジスモンチの曲では一、二を争う人気曲「Frevo」と「Karate」をメドレーで弾くなど、予想をしない流れにはビックリしつつも、グイグイと彼の音楽世界に引き込まれていく。身をゆだねることの心地よさ・・・。
アンコールも含めてピアノで8曲の演奏。鳴り止まぬ会場の拍手にこたえ、何度もステージに戻って挨拶をするジスモンチの表情にも満足そうなものが浮かぶ。以前の公演ではプロモーターとの関係から「二度と日本では演奏をしたくない」といったといううわさを耳にしたが、このファンの歓声を受け止めてぜひとも日本公演を続けて欲しいという思いを強くした。
前回のライブはこれまでに見たもののベストと思っていたので、正直なところそれを上回ることはないだろうと思って会場に出かけた。しかし、そんな思いは軽く吹き飛ばされるほどの演奏。このすばらしい音楽を、家人とも共有できたことはこの上ない幸せ・・・。
当日のセットリスト
<追記>
今年の夏に開催予定の『第24回 〈東京の夏〉音楽祭2008』での来日が決まったようである。詳細は音楽祭のオフィシャルHPをごらんいただきたい。
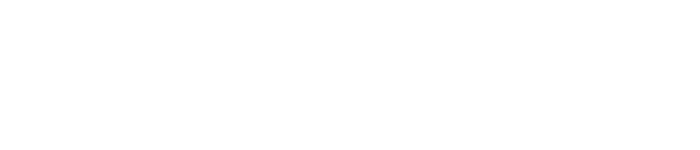
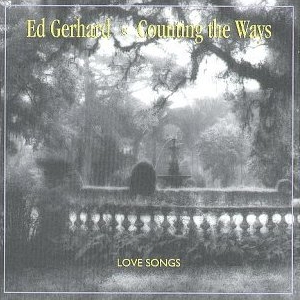
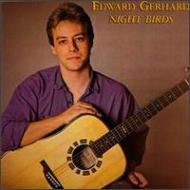

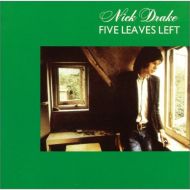

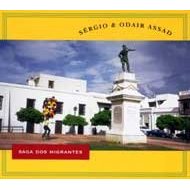
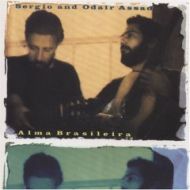 アサド兄弟のことを知ったのは、ある雑誌にギタリストの渡辺香津美氏が、今一番気になっているギターアルバムとしてアサド兄弟の
アサド兄弟のことを知ったのは、ある雑誌にギタリストの渡辺香津美氏が、今一番気になっているギターアルバムとしてアサド兄弟の