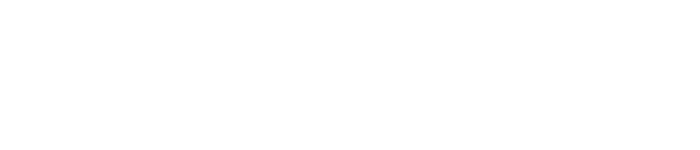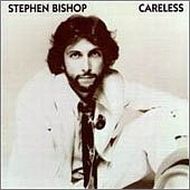Michael Hedges (g)
Michael Manring (b)
George Winston (p)
ウィンダムヒル・レーベルのギターもの、というと真っ先に出てくると誰もが思うのがマイケル・ヘッジスだろう。確かに、以前取り上げたアレックス・デ・グラッシに比べても、左手でのタッピングなどを初めとする斬新な演奏方法などからも、印象に強く残るプレイヤーだろう。好き嫌いは別にして、フィンガースタイルのインスト演奏をする人は、必ず一度はその演奏を耳にしているはずだし、コンテンポラリーな曲では、マイケルが礎を築いた演奏スタイルを何らかの形で取り入れたものも多い。
初期の作品からすでに傑作が多いが、今回はファーストアルバムを取り上げてみたい。ここでは、アレックスのときと同じようにErvin Somogyiのギターを半数以上の曲で使用している。Ervinの工房にいたとき、マイケルのことを聞いたことがあったが、残念ながらアレックスの場合とは違って、マイケルはソモギギターを所有してはいなかったそうだ。
ファーストアルバムを録音するにあたり、いいギターを探していたマイケルは、Windham Hillレーベルの主宰者ウィリアム・アッカーマンに相談したところ、Ervinとすでに面識があった、ウィリアムはすぐさま、彼の工房へと足を運んだ。たまたま、手元にあったギターをErvinは快くマイケルに貸し、そのギターを使ってこの作品の録音が始まったのである。
70年代の終わりから80年代の初めにかけてのソモギギターは、現在のようなフィンガースタイル向きと限定されるようなものでは必ずしも無かった。しかし、マーティンを初めとする当時主流だった工場製のものと比較すると、鳴りや倍音の響きに大きな特徴があった。
ギター演奏を始めて間もない段階では、いかに楽器を鳴らすかが大きな問題だ。しかし、どんどんレベルが高くなってくると、単に鳴らすだけではなく、響きを意図したようにコントロールできるかが重要なポイントとなる。鳴りのよい楽器であれば、必要に応じて、伸びている音を止める(ミュートする)というテクニックが不可欠なのだ。この点から考えると、Ervinの楽器は、その鳴りと倍音ゆえ、一般的な楽器よりもきちんとしたミュートのテクニックが無いと、いつまでもだらしなく音が鳴り響いてしまい、曲の進行感やハーモニーにも問題が出てきてしまう。
マイケルは、実は、この作品以降はErvinの楽器はほとんど使わず、マーティンなどの楽器をメインに使用することになる。ひょっとすると、マイケルのように左手でも弦をはじいて音を出すスタイルでは、自由に音をミュートするのが難しいということが、その背景にはあったのかもしれない。
1曲目に入っている「Layover」は、以前楽譜にもなっていたことがあり、マイケル好きの人が比較的簡単に挑戦する曲である。1998年に、サンフランシスコからゴールデンゲート・ブリッジを渡ってしばらく行ったサン・ラファエロという街でギターの展示会があった時の事である。Ervinのアシスタントとして私も会場で手伝っていたところ、中国系アメリカ人の男性が、ブースにやってきて試奏させて欲しいといった。彼がおもむろに弾き始めたのが、この「Layover」だった。ほとんどノーミスで完璧に近い演奏に、Ervinともどもビックリしたものだった。途中で、演奏を聴きつけて、少しずつギャラリーが集まるような状態になっていた。
弾き終わった後、「一度、マイケルが実際にレコーディングで弾いたソモギ・ギターでこの曲を弾いてみたかったんだ」と彼がいったのを聞き、わずかその半年くらい前に交通事故でこの世を去ったマイケルの根強い信奉者がどこにでもいることを実感した。
集まったギャラリーの中には、サンフランシスコをベースに演奏活動や、ライブの企画で中心的な働きをしているブライアン・ゴアというギタリストがいた。彼は、すぐさまその男性に声をかけた。「オリジナルの曲はないの? あれば、今度やるライブに一緒に演奏しないか。」と。しかし、彼の答えは、「オリジナルの曲はないんだ・・・。ただ、好きな曲をコピーして弾いているだけだよ。」というものだった。
ブライアンにしてみれば、これだけギターが弾けるなら、自分で作った曲を演奏していてもおかしくは無いと思ったようだ。横で聞いていた私は、なんとなくこの中国系アメリカ人に、日本人にも通ずるようなメンタリティを感じ、共感できるものがあった。
でも、今なら少し考え方が違う。うまくギターが弾けるようになるのは、自分にとっては楽しいことである。しかし、人の心を動かすのは、表現としての音楽で、演奏テクニックではない、と。
テクニック云々とはまったく別の次元において、オリジナルとしてのマイケルの素晴らしさ、すごさは筆舌に尽くしがたいものがある。