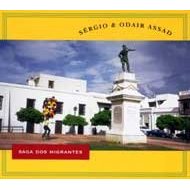●Sergio & Odair Assad: Saga dos Migrantes
コンスタントに活動をしているクラシック・ギターのデュオでは、まず紹介しなければいけないのがアサド兄弟だろう。兄セルジオと弟オダイルは4歳違い。自らたちを「4歳離れた一卵性双生児」と称することもあるが、その言葉通り、完璧なアンサンブルには思わずため息が出てしまうほどだ。
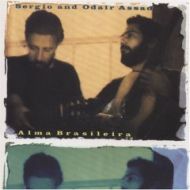 アサド兄弟のことを知ったのは、ある雑誌にギタリストの渡辺香津美氏が、今一番気になっているギターアルバムとしてアサド兄弟の『ブラジルの魂』をあげていたからだ。このアルバムには、ジョン・マクラフリンとパコ・デ・ルシアの演奏で有名になった、エグベルト・ジスモンティ作「Frevo」が入っていて、今回紹介する作品と甲乙つけがたい名盤といえよう。
アサド兄弟のことを知ったのは、ある雑誌にギタリストの渡辺香津美氏が、今一番気になっているギターアルバムとしてアサド兄弟の『ブラジルの魂』をあげていたからだ。このアルバムには、ジョン・マクラフリンとパコ・デ・ルシアの演奏で有名になった、エグベルト・ジスモンティ作「Frevo」が入っていて、今回紹介する作品と甲乙つけがたい名盤といえよう。
ギターものはほとんどなんでもといっていたわりには、クラシック関係はほとんど聴いていなかった当時、「香津美さんが薦めるくらいだから・・・」と手に入れて聴いてみたところ、何となくピンと来なかったというのが正直な感想だった。アンサンブルの凄さは十分わかるのだが、生ギターのアンサンブルといえばスーパー・ギター・トリオ系のものを愛聴していた耳には、何だが音が遠く、きれいにまとまりすぎているような感じがしたのだった。
それでも、何度も聴き続けているうちに、だんだんとその素晴らしさがわかってくるようになる。なんといっても特筆すべきは、タッチである。二人のつむぎ出す音の立ち上がりの見事なこと。あまりに流暢なので、さらった聞き流してしまいそうなフレーズも、大きな流れの抑揚がしっかりあるのだ。
二人の愛器は、ニューヨーク在住のトーマス・ハンフリー作のもの。トムはギターの表面板に対して指板の位置を上げるレイズド・フィンガーボードというシステムを普及させた張本人。最近では、日本の製作家でもこのスタイルを用いている人がいる。表面板裏のブレイシングと呼ばれる補強兼音響コントロール部材にも、独自の工夫が施されていて、彼の楽器の音の立ち上がりの素晴らしさは誰もが認めるところであろう。
ギター専門誌のインタビューで、表面板を含めた音作りの考え方を語っていた記事は、アメリカにいるときに熟読したものだった。東海岸在住ということで会うチャンスがなかったが、いつかは会ってみたい製作家の一人だ。
アサド兄弟は、バッハに始まり、古典的なレパートリーの演奏も素晴らしいが、やはり「南米モノ」を弾かせると、並ぶものがないほどだ。本作では、クラシック・ギタリストがレパートリーとしていることの多いピアソラ、ヴィラ=ロボスをはじめとし、セルジオ・アサド自身の曲や、ブラジルの異才エグベルト・ジスモンティの曲も取り上げている。作曲のみならず、セルジオの編曲センスも素晴らしく、あたかもギター曲であったかのような素晴らしいアレンジを、このアルバムでもじっくりと堪能できよう。
毎年といっていいくらい来日を重ねているアサド兄弟。次に日本に来たときには、ぜひともコンサートに足を運ぼうと思う。
ちなみに、このジャケットの写真は、Joel Meyerowitzによるもの。彼の代表作ともいえる、ケープコッド湾で撮影した写真集もよく眺めたものだ。カラーでのスナップ的な風景写真の先駆者であるが、彼独特の雰囲気が、このジャケット写真からも伝わってくる。