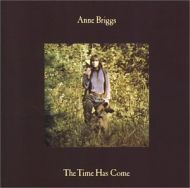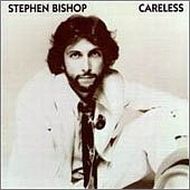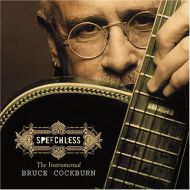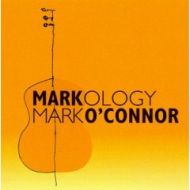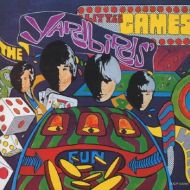●Nick Drake: Five Leaves Left
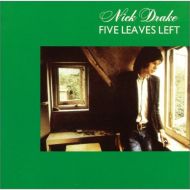
Nick Drake (vo, g)
Paul Harris (p)
Richard Thompson (g)
Danny Thompson (b)
Rocki Dzidzornu (per)
Clare Lowther (cello)
Tristam Fry (ds, vib)
以前は、洋楽というとほとんどアメリカのものを聴いていたような気がするけれど、最近手を伸ばすのは、圧倒時にブリティッシュものが多い。若い頃にはじっくりと向き合ってこなかったものを、あらためて丹念に聴いていくと、実にしっくりと来る感じのものが多い。
アメリカ、それもウエストコーストの音楽と比較すると、ブリティッシュのものは、マイナー(短調)な曲はもちろんのこと、メジャー(長調)であっても、底抜けに明るい感じは決してなく、どこかに影を落としているような印象が強い。イギリス特有のあのどんよりとした気候と、ついついリンクしているかのような気になってしまう。
ニック・ドレイクはそんなブリティッシュの中にあっても、一段とダークでメランコリックな音楽で知られる。弱冠20歳でニックは、当時凄腕のプロデューサーとして知られていたジョー・ボイド(Fairport ConventionやThe Incredible String Bandのプロデュースで知られる人物)と契約を結び、ファーストアルバムとなる本作をリリースしたのは1969年。彼が21歳のときだった。
バックを支える中心メンバーはPentangleのベーシスト、ダニー・トンプソンとFairport Conventionのギタリスト、リチャード・トンプソン。当時を代表する人気グループのメンバーが新人をサポートするも珍しいことだったようだ。
レコード会社が提案していたストリングス・アレンジャーに首を横に振り、ニックのケンブリッジでの友人ロバート・カービーにアレンジをさせるなど、20歳そこそこの新人らしからぬ逸話も残っている。
一度足を踏み入れてしまうと、抜け出せないほど深くて暗い孤独の闇が、ニックの世界には広がっている。時折差し込むかすかな光も、次の瞬間には「やはり幻だった」と思ってしまいそうな暗闇の中。「自分とは縁のない世界であって欲しい」と思いつつも、このアルバムを聴くと心の中の何かが震えだす。
専門家の間では評価が高かったにもかかわらず、リリースした3枚のオリジナルアルバムは、いずれもセールス的には振るわなかった。そんな状況が、ニックをどんどんと追い詰めていったのだろう。3枚目の『Pink Moon』を発表した後、精神状態が一層不安定になっていく。もともと、音楽制作をしている間はライブ演奏をほとんどしていなかったが、この頃からは音楽制作自体も休止すると口にするようになっていく。ただ、他のアーティストに向けた曲作りだけは続けたかったようである。
そして1976年11月26日。息を引き取っているニックが発見される。まだ26歳だった。前の晩に抗うつ剤を過剰摂取していたのが死因とされた。枕元には母親が好きだったというカミュの詩集。自殺説が強い中、彼の家族はあくまでも誤って過剰摂取をしたことによる事故死だと主張していたという。
彼の心の中は、闇に閉ざされたままだが、残した素晴らしい音楽は、人々の心を揺さぶり続けるだろう。